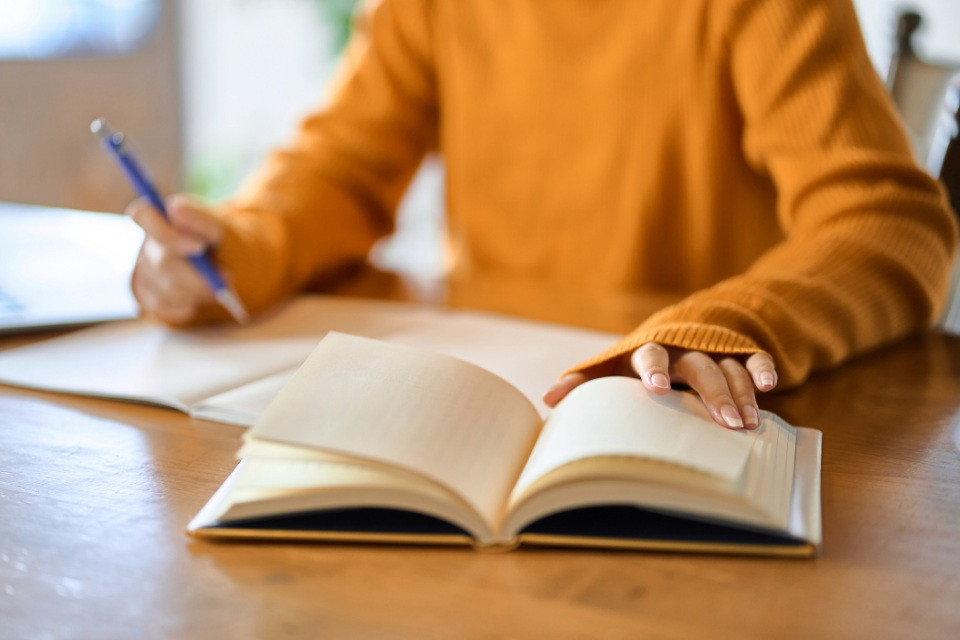ドラマ『明日はもっと、いい日になる』の現場って?児童福祉司・児童心理司のリアルな仕事とは

2025年7月期の月9ドラマ『明日はもっと、いい日になる』で注目を集める児童福祉の現場。林 遣都さん演じる蔵田 総介は児童福祉司、生田 絵梨花さん演じる蒔田 向日葵は児童心理司として、虐待や貧困、育児放棄などの困難を抱える子どもたちに寄り添う姿が描かれています。
ドラマをきっかけに「実際の現場もドラマと同じ?」「私も目指してみたい」などと関心を持つ人もいるのでは。この記事では、困難な状況にある子どもたちを支える2つの専門職について、15年のキャリアをもつベテラン児童福祉司の方に、リアルな現場の実態と併せて詳しく解説いただきます。
【INDEX】
【児童福祉司編】
児童福祉司はどんな仕事?どうやってなれる?
児童福祉司の主な業務
児童福祉司になるには
採用プロセス
児童福祉司の採用後のプロセス
ドラマでは描かれない児童福祉司のリアルな現実
【児童心理司編】
児童心理司の仕事とは?児童福祉司との違い
児童心理司の主な業務
児童心理司になるには
採用プロセス
チームで子どもを支える、児童心理司の現場
【児童福祉の現場】
児童福祉の今。深刻化する現状
児童福祉現場からの声
需要はますます増える! 児童福祉司、児童心理司の今後
【児童福祉司編】児童福祉司はどんな仕事?どうやってなれる?
命を守る最前線の専門職
児童福祉司とは、地方公共団体に福祉職として採用され、児童相談所に配属される公務員で、18歳未満の子どもの安全と安心を守り、保護者の相談に応じることを主業務とする専門職です。「子どもの最善の利益」を目指して時には家族と対立してでも子どもの命と権利を守る、大きな責任とプレッシャーを伴う仕事となっています。
児童福祉司の主な業務
児童福祉司は、虐待や養育困難の通告・相談への対応から、家庭訪問や関係機関との連携による状況調査、支援計画の作成と実施、安全確保のための一時保護や法的手続き、そして家庭復帰後の継続的なフォローまでを担っています。
1:相談・通告の受付と対応
・虐待や養育困難に関する通報(189など)や相談の一次対応を行う。
・子どもや家庭の状況を確認し、必要に応じて現場に駆けつける。
・虐待通告があれば48時間以内に安全確認を行うことが必須。深夜や休日でも関係なく、「今すぐ子どもを保護すべきか」という重大な判断を迫られることも。
・家庭に入り込み、時には警察と連携して一時保護を実施する場合もある。
2:調査とアセスメント
・家庭訪問や保護者・子どもへの面談を実施。
・学校・医療機関・警察などからの情報収集を行う。
・子どもが安全に暮らせる環境かどうかを総合的に判断する。
・「この家庭で子どもは安全か」「保護者に養育能力はあるか」を客観的に評価する専門的な目が求められる。
・家庭復帰を目指す場合は、保護者への具体的な指導やカウンセリングも行う。
3:支援計画の作成と実施
・家庭内での生活を改善するための支援プランを作成。
・保護者への助言やカウンセリングを実施。
・必要に応じて、里親委託や施設入所の調整も行う。
・子どもが安全かつ安定して暮らせる環境を整えることが目的。
4:一時保護・法的対応
・子どもの安全が確保できない場合の一時保護措置を実施。
・家庭裁判所への申し立てや親権停止など、法的手続きを行う。
・家庭裁判所での手続きや法律に基づく対応は重要な業務の1つ。
・医療機関、学校、警察など多くの関係機関との調整役も担う。
5:継続的なフォローアップと家庭復帰支援
・家庭復帰が実現しても、その後の生活が安定して続くことが重要。
・家庭復帰後も定期訪問や面談を行い、再発防止を図る。
・保護者が養育を継続できる環境が維持されているか確認する。
・必要に応じて地域の支援サービスや相談機関につなぐ。
・支援が不要と判断されるまでケースを継続的に担当する。
児童福祉司になるには
児童福祉司になるために必須なのが「任用資格」。「任用資格」とは、採用されるために最低限持っていなければならない資格のことです。任用資格取得には主に以下の3つのルートがあります。
1.任用資格を取れる大学の卒業(最も一般的なルート)
4年制大学で指定科目を履修して卒業
※必修科目:社会福祉概論、児童福祉論、心理学、教育学、社会学など
※心理学、教育学、社会学、社会福祉学などの学部・専攻の場合、ほぼ任用資格取得の要件を満たしているといえる。
2.国家資格ルート(難易度は高いが信頼度も高まる)
「社会福祉士」または「精神保健福祉士」の国家資格取得
※資格取得後、実務経験なしで児童福祉司任用資格を得られる。
3.実務経験ルート(社会人からの転職など)
高校卒業後、児童福祉事業に2年以上従事
都道府県知事指定の講習会(約1年間)を修了
採用プロセス
任用資格を取得後、各自治体の公務員採用試験(福祉職)に合格する必要があります。
筆記試験
・教養試験(一般常識、時事問題など)
・専門試験(社会福祉、児童福祉、心理学など)
面接試験で重視される点
・児童福祉への深い理解と熱意
・困難な状況でも冷静な判断ができる能力
・コミュニケーション能力と調整力
・ストレス耐性と継続的な支援への意欲
児童福祉司の採用後のプロセス
新任者は1〜2年間にわたり実地研修を受講します。
基礎研修(入職1年目)
・児童福祉法などの法的知識
・面接技法、記録の書き方
・虐待の見極め方と対応方法
・緊急時の対応手順
実践研修(入職2年目)
・先輩職員とのペア活動
・実際のケースワーク体験
・家庭訪問の実践
・関係機関との連携方法
児童福祉司は、法律や制度に基づき、家庭や関係機関と連携しながら課題解決を進める公的専門職。現場では多様で複雑なケースに向き合い、限られた資源の中で最適な対応を判断する力が求められます。
ドラマでは描かれない児童福祉司のリアルな現実
ドラマでは、1人の児童福祉司の担当ケースは数件、そして1つひとつのケースに対して多くの時間を割くことができるように見えますが、実際の現場ではそんなことはありません。
実際の現場では、1人の児童福祉司が70〜100件ものケースを同時に抱えることが常態化しており、多忙を極めています。虐待の再発リスクを常に考慮しながら、限られた人員と予算の中で最適な支援を模索し続ける必要が。多様で複雑なケースに向き合いつつ、最適な対応を判断していくことが必須であり、粘り強さが求められています。子どものためにと努力しても、それが理解されず、保護者から恨まれたり、脅迫を受けることも。
それでも「この子を守らなければ」という使命感をもった児童福祉のプロフェッショナル、それが児童福祉司といえるでしょう。
【児童心理司編】児童心理司の仕事とは?児童福祉司との違い
子どもの心に寄り添う専門家
児童心理司は、心理学の専門知識を活かして子どもの心理状態を評価し、適切な支援方法を提案する専門職です。子どもの「見えない傷」を発見し、癒やしのプロセスに伴走する重要な役割を担います。
児童心理司の主な業務
児童心理司の仕事は、目に見える変化が現れるまでに長い時間がかかることも多く、地道で継続的な支援が求められます。虐待を受けた子どもが再び人を信頼できるようになるまでには、何年もかかることもあります。
1:心理診断・検査の実施
・WISC知能検査や発達検査、描画テストなどを用い、子どもの認知能力や心理状態を客観的に評価。
・発達障害の有無や、虐待によるトラウマの程度なども専門的に判断。
・検査結果を分析し、報告書として支援チームに共有。
2:心理アセスメント
・面接や観察を通して、子どもの心理状態や行動特性を総合的に評価。
・家族関係や生活環境が子どもに与える影響を分析。
・心理面から見た支援の優先順位を明確にし、児童福祉司と情報を共有。
3:心理療法・カウンセリング
・プレイセラピー(遊戯療法)、認知行動療法など子どもの年齢や状況に応じた心理療法を実施。
・言葉では表現できない子どもの気持ちを、遊びや絵を通して理解し、心の回復を支援。
・保護者のメンタルヘルスケアなど、心理的課題に応じた介入を行う。
4:支援計画への参画と提案
・検査・アセスメントの結果をもとに、心理面からの支援計画を提案。
・児童福祉司や医師、学校の教員などと連携し、包括的な支援方針を決定。
・必要に応じて医療機関への受診を勧め、治療と福祉支援をつなげる。
5:継続的な心理的フォロー
・支援開始後も定期的に心理状態を確認し、支援内容を見直す。
・子どもや家族の変化に合わせてカウンセリング方法や頻度を調整。
・長期的な成長や社会適応を見守り、必要があれば関係機関と再度連携を取る。
児童心理司になるには
必要な学歴と資格
児童心理司になるには、心理学の専門的な知識と実践経験が不可欠です。
基本要件
・4年制大学で心理学を主専攻として卒業
・心理学関連科目を一定単位数以上取得
・統計学、実験心理学、発達心理学、臨床心理学などの履修
推奨される進路
・臨床心理学系大学院の修士課程修了
・実習経験やスーパービジョンの受講歴
・心理検査の実施経験とカウンセリング技法の習得
有利な資格
・「公認心理師」(国家資格)
・「臨床心理士」(民間資格だが児童分野では高評価)
・「学校心理士」(教育現場での心理支援専門資格)
採用プロセス
各自治体の心理職採用試験に合格する必要があります。一般的な公務員試験とは異なり、心理学の専門知識や実践能力が問われ、現場経験の有無なども採用時には重視されます。
求められる経験
・病院や相談機関でのカウンセリング
・心理検査の実施・解釈の実務
・児童・思春期分野での実習
・発達障害や虐待ケースへの対応
チームで子どもを支える、児童心理司の現場
児童心理司は、検査やカウンセリングだけでなく、子どもの心の安全を守るためにチームで支援方針を作る重要な役割を担います。現場では、トラウマを抱える子ども、発達障害を持つ子ども、家庭環境の影響で不安定な情緒を示す子どもなど、非常に多様で複雑なケースに向き合う必要も。
ドラマでは、1人の心理司が1件のケースに時間をかけて向き合っているように描かれることもありますが、実際は複数のケースを同時進行で担当します。継続的なカウンセリングの合間に、学校や医療機関との連絡調整、会議での報告、記録作成などに追われることも多く、時間的にも精神的にも負荷はとても大きいもの。
それでも、子どもが少しずつ表情を取り戻し、安心して生活できるようになる瞬間に立ち会えるのは、この職ならではの大きなやりがいといえるでしょう。
児童福祉の今。深刻化する現状
虐待相談対応件数は年々増加傾向にあり、令和2年度からは年間20万件を超え、令和5年度は225,509件となりました。児童福祉司、児童心理司の1人当たりのケース数が過多で十分な支援ができない現実があり、夜間・休日対応による長時間労働も問題となっています。精神的負担の大きさによる早期離職率の高さや、経験豊富な職員の不足も深刻です。
また、「家族を引き離す」という批判的な見方や、予防的支援の重要性への理解不足など、社会の理解不足も課題となっています。
児童福祉現場からの声
保護した子どもは、いつかは家庭に戻すことが基本方針ですが、この「再統合」は保護よりさらに難しい課題。家庭環境の改善や親子関係の修復には長期的で複雑な支援が必要で、大学を出たばかりの若い職員に担わせるにはあまりに重い責任だという意見も。また、支援と介入を同じ機関が担うことの難しさも指摘されており、現場からも同じ声が聞かれます。
業務中には、感謝されるよりも怒られたり、嫌われたり、恨まれることの方が多く、「褒められることはほとんどない」というのが実情となってしまっており、心理的負担は想像以上に大きいものです。
さらに、常勤の正規職員を十分に確保できておらず、非常勤や任期付き職員で数を補っている職場も少なくありません。これにより経験やノウハウの蓄積が難しく、支援の継続性や質への影響が懸念されています。
需要はますます増える! 児童福祉司、児童心理司の今後
前述のような過酷な状況下でありながらも、児童福祉司や児童心理司は、今後ますます必要とされる見込みに。背景には、2022年の児童福祉法改正によって市町村でも相談や支援を行う体制が広がったことや、2023年に発足した子ども家庭庁によって政策が一元化され、子どもや家庭への支援がより計画的に進められるようになったことがあります。また、「困ってから支援する」のではなく、「困る前から支援する」虐待の未然防止、予防的支援に力を入れる動きも進行中です。こうした流れに対応するため、職員向けの研修制度は体系化・高度化され、医療・教育・警察など他分野との連携も強化されています。さらに、支援の効果を科学的に裏付ける(エビデンスに基づく)方法の確立も求められています。
将来は、行政や児童相談所での勤務にとどまらず、民間企業での児童福祉コンサルタント、NPO法人での専門的支援、大学教員や研究職、さらには独立開業など、多様なキャリアパスが広がっていくでしょう。
子どもの命を守る「最後の砦」となる仕事
ドラマ『明日はもっと、いい日になる』で描かれる児童福祉の現場は、確かに困難に満ちています。しかし、そこで働く児童福祉司と児童心理司たちが、子どもたちの「明日」を変える可能性を信じて日々奮闘していることも事実です。
決して楽な道ではありませんが、子どもたちの未来のために自分の専門性を活かしたいと考える方、社会の最も弱い立場にある人々を支えたいという強い意志を持つ人には、やりがいのある意義深い職業。
もし目指してみたいと思った場合は、まずはボランティア活動への参加、インターンシップなどを通じて、児童福祉の現場を知ることから始めてみては。あなたの「子どもたちを守りたい」という気持ちが、きっと多くの子どもたちの「明日」を照らす光になるはずです。
お話を伺ったのは……
※児童福祉の制度や資格要件は、現在頻繁に変更されています。進学や就職を考える場合は、最新の情報を公的機関などで確認してください。
こちらの記事も要チェック!◆夏に「梅干し」がおススメな本当の理由を薬膳の視点から解説!
◆3歳から飲める花粉症対策ハーブティー。アレルギーには継続ケアが大切!
◆2025年版!取って良かった資格・検定ランキングTOP10
◆「角川武蔵野ミュージアム」でイマジネーションを刺激する1日を
◆脳疲労を加速させる行動があった。勉強の合間の逆効果リフレッシュ法とは?