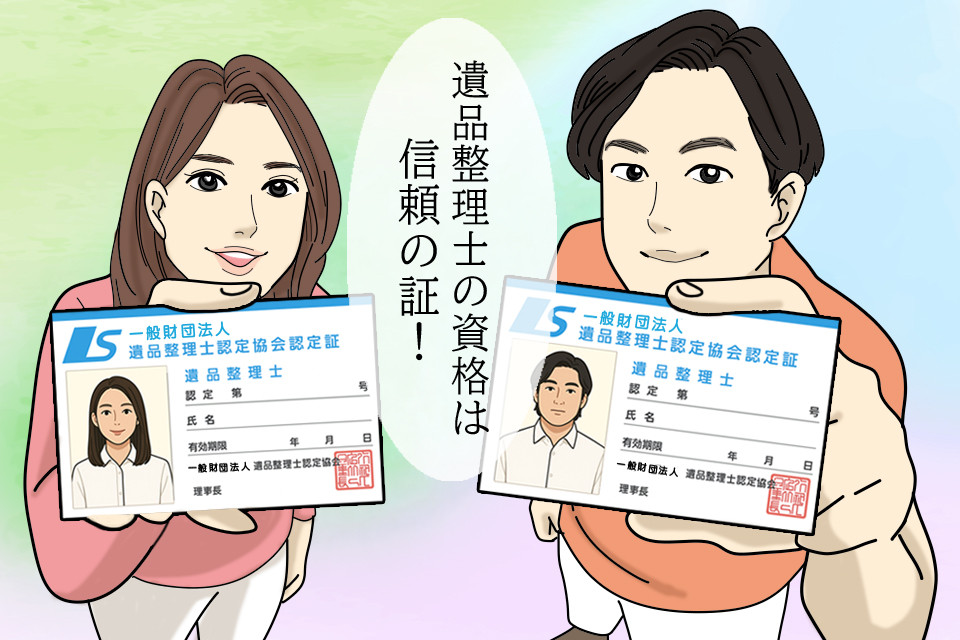ドラマ『終幕のロンド』でも話題。20代で遺品整理士の道を選んだ若手が語る“現場のリアル”
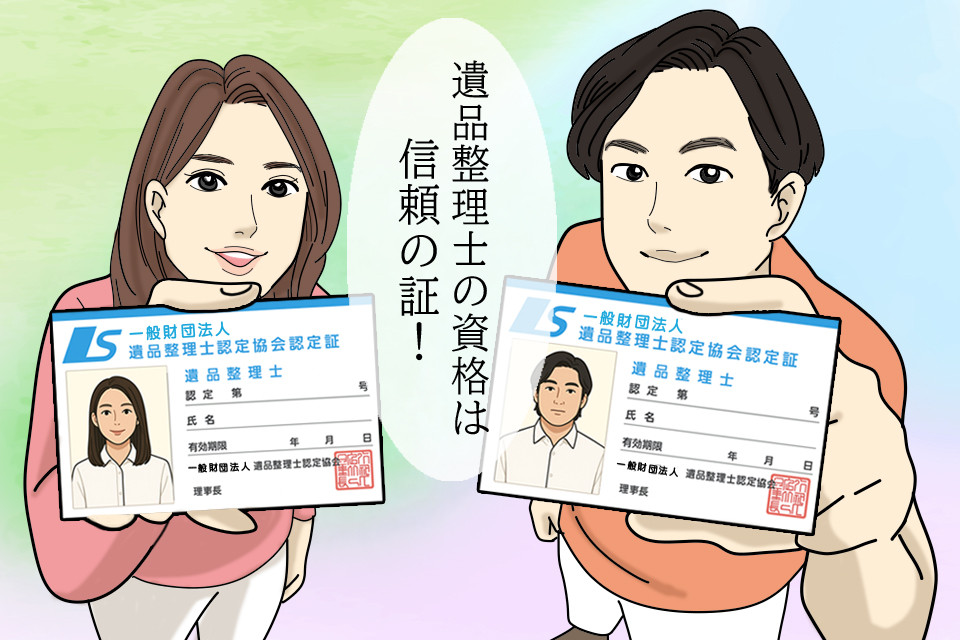
親世代の高齢化が進み、多くの人が直面する可能性がある「遺品の整理」。その専門家が「遺品整理士」だ。しかし、現場の実態や仕事の内容は、まだ十分に知られていないのではないだろうか。
2025年10月スタートのドラマ『終幕のロンド』で注目が集まる遺品整理という仕事。作中では、遺品整理人として働く主人公が、故人の想いと残された家族の心に寄り添いながら、それぞれの“再出発”を見守る様子が描かれている。
現実の現場では、どんな人が、どんな想いでこの仕事に向き合っているのか。20代の若手遺品整理士の2人に話を聞いた。
お話を伺ったのは……
金子 美優さん
大阪を拠点に夫婦で遺品整理会社を経営。実父の死をきっかけにこの仕事の道へ。遺族の想いに寄り添う姿勢を信条としている。
太田 貴也さん
東京を拠点に遺品整理・買取を手がける。リユース業界での経験を活かし、スピーディかつ丁寧な整理を両立するサービスを目指している。
20代で「遺品整理士」を仕事にした理由
「父が亡くなったのは、私が26歳の時でした」(金子さん)。
大阪で夫とともに遺品整理会社を経営する金子 美優さん(29)。46歳で急逝した実父の突然の死に衝撃を受けたのと同時に、その後の遺品整理を通して“親族の死や遺品と向き合うことの難しさ”を痛感したという。
当時は保険会社の営業職をしていたが、この経験がキッカケとなり、まずは「リサイクル業」を立ち上げることに。一方、現在は事業パートナーでもある夫は別の会社でリフォームや不用品回収の仕事をしていた。
「遺品を前にすると、感情が先立ってしまって、なかなか向き合えない。そんな人たちの力になりたいと思いました。リサイクルと不用品回収を組み合わせたら遺品整理の事業ができるのではと考え、遺品整理会社を設立。2022年のことです」(金子さん)。
「ただの片付けじゃない」遺品整理で知った仕事の真髄
一方、東京を拠点に遺品整理・買取を手がける太田 貴也さん(28)はリユース業界で働く中で、思いがけず“遺品整理”という仕事に出会った。
「お客様の中に、ご家族の遺品を整理してほしいという相談が少なからずあって。話を聞くうちに、『遺品整理』という仕事があることを初めて知りました」(太田さん)。
身近な「買取」から、“想いの残るモノ”を扱う世界へ。不用品回収の仕事をしていた友人に声をかけ、2023年末、遺品整理の世界へ飛び込んだ。
「実際に始めてみると、これはただの片付けではないとすぐに分かりました。ご遺族の気持ちに寄り添うことが何よりも重要な仕事なのだ、と。最初の現場では緊張で手が震えましたが、最後に『ありがとう』と感謝の言葉をいただいて、胸の奥が熱くなるのを感じました」(太田さん)。
経験を重ねて1年半。今では、冷静さと丁寧さを両立させながら、多くの現場で“想いに寄り添う整理”を続けている。
資格は「信頼の証」になる
金子さんも、太田さんも遺品整理の仕事をすることを決意して最初にしたことは「遺品整理士」資格の取得だった。
「遺品整理士」の資格を取得するには、「一般財団法人 遺品整理士認定協会」のHPから遺品整理士養成講座に申し込み、テキストとDVDで学習し、レポートを提出することが求められる。合格率は65%程度だ。
「仕事が終わった後や、週末に集中して取り組み、勉強を初めて1カ月程で取得できました」(金子さん)
とはいえ、やはり簡単ではない。太田さんは一度、不合格を経験したそう。
「不合格になってしまったときは、まだ遺品整理士としての覚悟が足りなかったのだと思います。この資格は、単なる知識だけでなく、受験者の姿勢まで問うものであると実感し、おこがましいですが、資格に対する信頼度が上がりました」(太田さん)。
遺品整理の仕事をする上で、「遺品整理士」の資格は法律上必須ではない。それでも2人が資格を取得したのは、顧客からの信頼感や安心感に繋がると考えてだった。実際に、「資格を持っている方に頼みたかった」と顧客から直接言われたこともあり、この判断が正しかったと実感しているという。
「遺品整理士」資格取得時に勉強したこと
顧客から信頼を得られる理由は、「遺品整理士」資格の学習内容にある。不用品処分のための法律や、処分方法といった実践でも必須の知識、そして遺品整理士としての「心構え」までに及ぶ。遺品整理の仕事には、知識だけでなく思いやりと心配りが欠かせないからだ。
「合否を判定する最終レポートでは、具体的に『この場面でどのような言葉をご遺族にかけますか』といった内容も出題。故人と遺族の想いに寄り添う姿勢を学びました」(金子さん)。
資格取得は、知識と心構えを学ぶだけでなく、取得後のサポート体制も大きなメリットなのだとか。
「取得する前は分かっていませんでしたが、想像以上に遺品整理士認定協会のサポートが手厚くて、良い意味で驚いています。分からないことがあれば電話をすればすぐに教えてくれる。定期的に講習も開催されているので、知識をアップデートできるし、仕事の幅も広げることができます。同業者との交流会もあって、会社を立ち上げたばかりの頃は本当に助けられました」(金子さん)。
協会が運営するサイトに登録すると、依頼が紹介される仕組みもある。こうして、資格取得とサポート体制を整えた2人は、本格的に遺品整理の仕事をスタートさせた。
仕事の進め方は?時間や金額も
では、実際の仕事はどのように進むのか。依頼主の多くはご遺族だ。
料金はワンルームで10万円前後、一軒家で30万円から100万円と幅がある。「ワンルームなら2人で伺って、だいたい2時間ほどで片付けられます」(太田さん)。
価格を左右するのは、物量と処分の難易度。「例えばペンキなど産業廃棄物扱いになるものがあると処分代が変わります」(金子さん)。
事前に必ず現場を確認して見積もりを出す。作業では1つひとつ丁寧に、要不要を確認しながら進めていく。
「遺品整理の業務だけでなく、ご説明やお声がけまで、『頼んで良かった』と思ってもらえるように丁寧さを心掛けています」(金子さん)。
その丁寧さが求められる理由は、依頼主の立ち会いは必須ではないため、その場にいないケースも多いからだ。処分の判断に迷うものは一度取り分け、後で依頼主に確認してもらう。小さな確認を積み重ねながら進めていく——そんな心配りこそが、遺族に寄り添うこととなり、信頼に繋がっている。
「本当にこれを捨てていいの?」悩む依頼主に寄り添う
現場で最も時間がかかるのが、依頼主との「仕分け」の時間。
「一度袋に入れたものを『やっぱりもう1回見せて』って取り出されるなど、なかなか進まないことはよくあります。スケジュールはもちろんあるのですが、急かしたくないので、できるだけ見守るように。依頼主様の様子を伺いつつ『どうですか』などと声を掛けるようにしています」(太田さん)。
金子さんも笑いながらうなずく。
「一度確認し始めると、終始『これはどうしよう』『こっちもちゃんと確認したい』と迷う方は多いです。一方で納期もある。お客様の気持ちに寄り添いながらも、時間内に終わらせるのがプロの仕事だと思っています」(金子さん)。
また、依頼の中には売却・管理の都合で急いでいることが多い。「とにかく家を空にしてほしい」と、効率を最重視する依頼の場合、短期間での仕分け・搬出や産廃の処理手配など、段取り力と人手を重視した対応が必要だ。
「空き家を放置すると火事のリスクもあるし、空き巣も入りやすい。防犯上や衛生面でも良くないので、早めに整理したいというご相談が増加している印象です」(金子さん)。
「ありがとう」の言葉が、仕事を続ける理由
遺品整理士は必然的に「死」と向き合うシチュエーションが多い。辛くならないのだろうか。
「作業を終えてご挨拶する頃には、お客さまの表情が明るくなっていることが多いんです。感謝の言葉をいただけると、“役に立てた”という実感がわき、毎日やりがいを感じながら働けています」(太田さん)。
とはいえ、現場は決して楽ではない。ペットの糞尿が放置された部屋や、ゴミで足の踏み場もない家、孤独死の現場など――。最近は、そうした依頼も増えているのだとか。
「『特殊清掃』が必要な現場では、鼻が麻痺するほどの臭いがすることもあります。慣れることはありませんが、誰かがやらなければなりませんから」(太田さん)。
こうした特殊清掃の現場には、専門的な知識や技術も欠かせない。遺品整理士認定協会では、消臭や感染対策などを学べる講習も用意されており、太田さんも実際に参加したという。
「現場の安全確保や手順を知っているだけで、対応の幅が大きく広がりました」(太田さん)。
それでも、どんなに知識を身につけても、現場が楽になるわけではない。では、なぜこの仕事を続けられるのか。太田さんは少し笑ってこう答えた。「もともとメンタルが強いこともありますが、始めようと思ったときに“覚悟”を決めました。そうじゃなかったら、この仕事はできません」。
最後に、この仕事に向いているのはどのような人かと聞いたところ、2人は「冷静さと、気持ちに寄り添える心配りができる人」と答えた。
「思いやりを持って、物を大切に扱える人。また、遺品整理の際に処分するかどうかしっかり確認しなければならないものと、そうでないものの判断力も必要です。遺品整理って、ただ片付けるだけの仕事じゃない。故人と遺族の想いを繋ぐ仕事だと思っています」(金子さん)。
金子さんと太田さんは資格取得までの道のりは異なるが、依頼主の「ありがとう」を聞くたび、この仕事を選んで良かったと感じているのだそう。20代で、人の生と死に向き合う2人の言葉には、確かな重みがあった。
次回は、「遺品整理」という言葉すらなかった頃からこの仕事を続けてきたベテラン遺品整理士の方に、当時の現場といまの違いを聞く。
こちらの記事も要チェック!◆夫・加藤茶の食道破裂時も「介護資格」があったから乗り越えられた
◆ハーブの魅力を最大限に引き出し活用、メディカルハーブコーディネーター
◆経理・事務職のリスキリングに役立つ資格3選!
◆薬膳資格。どんなことを学ぶ?費用や活用法を深掘り!
◆スマホ依存対策、小島よしお実家のユニークなルールとは?
文=かたおか 由衣
イラスト=めい