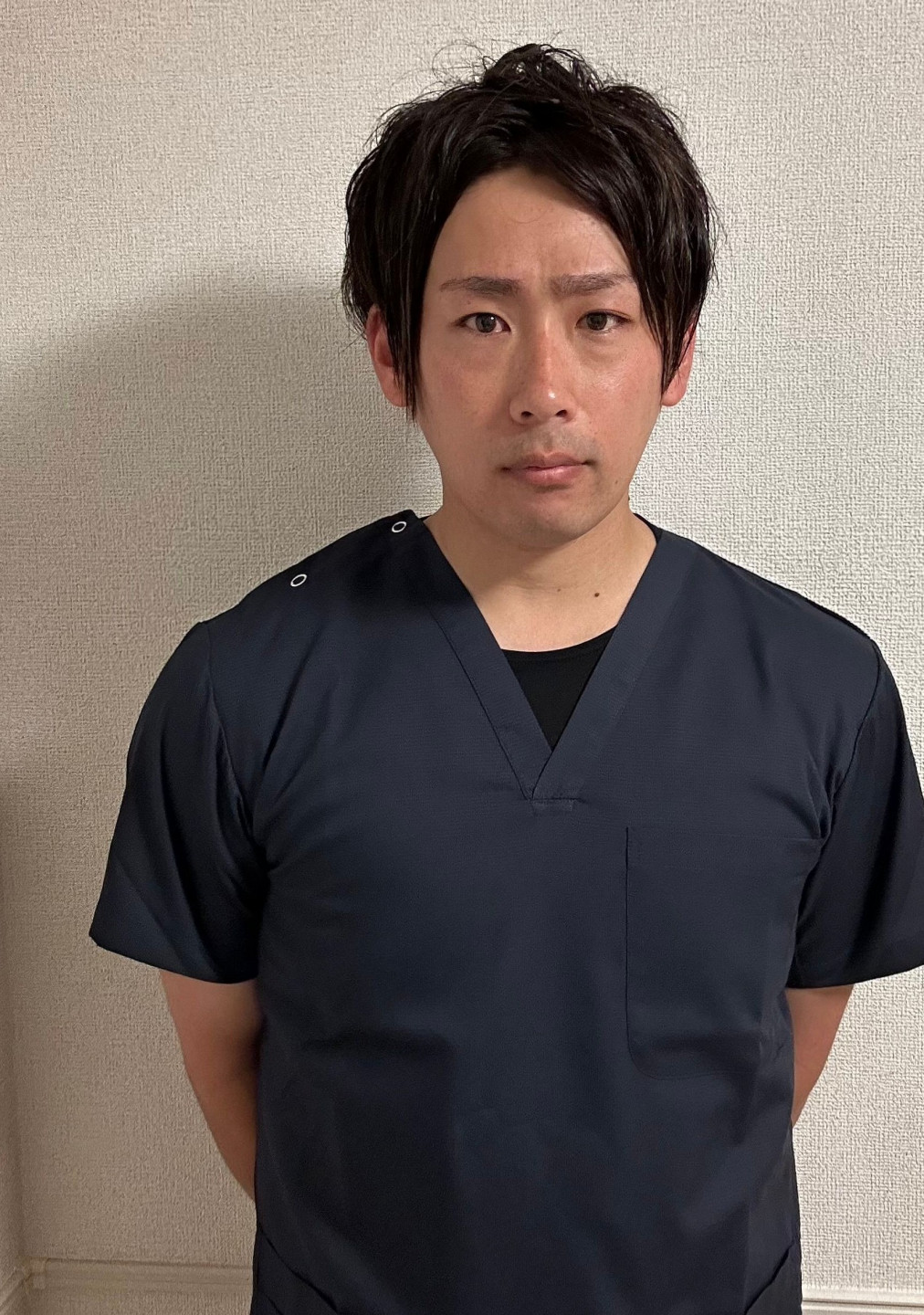『TOKYO MER』にも登場。「救急救命士」のリアルな現場をレポート!【しかくとはたらく。】

救急救命士と聞くと、どんなイメージがあるだろうか? 救急車で現場に駆けつけ処置を行い、命の危機に直面する患者を救う――そんなドラマのヒーローのような姿を想像する人も多いのでは。
現在劇場版も公開されている人気ドラマ『TOKYO MER~走る緊急救命室~』にも救急救命士が登場する。この作品の医療監修を務めたのが北里大学病院救命救急・災害医療センターだ。
今回は、その関連病院である北里大学メディカルセンター(埼玉県北本市)で勤務する現役救急救命士の鈴木 康史さんに、具体的な仕事内容やリアルな現場について話を聞いた。
『TOKYO MER~走る緊急救命室~』の現場とは? 緊急救急医療のリアル
4年制大学の医療系学部のコメディカル系(看護師や理学療法士など医師以外の医療職)の救命士コースで学び、救急救命士に。北里大学メディカルセンターでの勤務は昨年度からになるが、救急救命士としては8年目となる鈴木 康史さん。
多くの人が思い浮かべるのは「救急車に乗って現場に駆けつける姿」ではないでしょうか。実際、救急救命士(以下、救命士)はもともと救急車に乗るための資格で、日本の救命士の大半は消防署に所属しています。119番通報を受けて現場に駆けつけ、処置をしながら患者さんを病院へ搬送するのが主な仕事です。
ただ、私のように病院で働く救命士も。病院勤務の場合は、救急外来で医師や看護師とチームを組み、搬送されてきた患者さんの対応を行います。点滴や検査、処置のサポートなど、役割は多岐にわたるのが特徴です。
消防署のように119番通報を受けて現場に駆けつけることはありません。
病院救命士は、患者さんが病院に到着してからの対応を中心に、救急外来で医師や看護師と連携しながら幅広い処置を担います。そのような院内業務に加え、病院が所有する救急車に同乗して転院搬送や患者さんの迎え搬送を行うことも。
そうですね。私は新卒から病院勤務の救命士として働いていて、今年で8年目になります。当時は本当に珍しくて、同期の9割以上は消防署に就職していました。
8年前は病院で救命士が働く仕組みがまだととのっておらず、就職先といえば消防署が一般的でしたね。
実は学生の頃、ドラマ『コード・ブルー』を観て「ドクターヘリに乗りたい」と思った時期もありました。その延長で、海上保安庁での救難に携わる道もいいなと考えたこともあります。海上保安庁でも少人数ながら救命士の採用枠があるんです。
でも最終的には、“これから広がっていくであろう病院勤務の救命士”という道を選択。正直、当時は病院で救命士が何をするのかすら分かりませんでしたが、だからこそ未来を切り拓ける分野だと感じ、選びました。
いえ、現職は1年前からです。新卒で入った病院は、すでに救命士が数10名働いている、当時としては日本でもかなり先進的な病院でした。
そこで病院救命士の仕事を経験し、北里大学メディカルセンターへ、私が初の救命士として入職。
今、この病院には救命士が6名働いていて、救命士の存在意義が広がっています。救命士チームの立ち上げの時期から携われたのはとても大きな経験だったなと感じています。
北里大学メディカルセンターの救命士のうち3名は女性。鈴木さん(写真右から2番目)が所属する救急チーム。医師の田村 智さん(写真右)が司令塔となり処置を進める。
現在は、全国的にも病院救命士の活躍の場がどんどん広がっている段階。2021年に救急救命士法が改正されて、救命士が病院内で救命処置を行えるようになったこともこの流れを後押ししています。
医療現場の人手不足が深刻化する中、救命士が活躍できる場が広がることで、多くの方の命が救えるのではと思っています。
救命士の日々の仕事内容は?
DMAT(Disaster Medical Assistance Team/災害派遣医療チーム)隊員でもある鈴木さん。
そうですよね。医療系ドラマを見ると、大きな事故が多いですから。
でも、実際はそうでもないんです。ドラマのような大きな外傷があるケースは全体の1割程度で、むしろ少ないほう。一番多いのは発熱や頭痛、胸痛、呼吸困難など急病で受診される方ですね。
日によって幅がありますが、多いときには1日で20件近い搬送があることも。軽症から重症まで本当にさまざまで、立て続けに患者さんが運ばれてくることもあります。
気が抜けない現場であることは、ドラマや映画と同じかもしれません。
私もドラマも映画も観ています。実際にあんなに大きな事故はそうそうないけれど、処置などの際に手元を映す場面は、とてもリアルに忠実だな、と思いました。
病院救命士の未来。新しい技術と後輩指導の現場
病院救命士は歴史が浅く、教育の仕組みも病院ごとに違う。そのため、現場での整合性が保てるよう、病院全体の研修を活用したり、消防と合同の症例検討会に参加したりしています。
はい。最近では、自動心臓マッサージ機 が救急隊に導入されました。
救命救急士のポーチに必ず入っているセット。
従来は手で胸骨圧迫を行っていましたが、専用の機械を装着すれば自動で圧迫してくれるので、より安定した処置が可能に。とても便利な機器だと思います。
さらに当院では、AIを活用した新しいシステムの研究も進めています。スマホの画面を見せるだけで血圧や酸素飽和度といったバイタルサインを測定できるというもので、現在は実証実験中です。将来的には救命士が率先して扱うケースも出てくるかもしれませんね。
もちろん体力はあった方がいいですが、それだけで決まる仕事ではありません。
例えば消防勤務だと火災現場に入ることもありますが、病院勤務ではそうした体力的にハードな場面は少ないので、持病がある方や女性でも働きやすいんです。
実際、当院でも6名のうち半数が女性救命士。年々女性の割合は増えていて、現場でも活躍されています。
未開拓の分野を担う病院救命士
前述のように、救命士の資格は“救急車で活動すること”を前提につくられていますが、病院救命士が担える役割はまだ定められていない部分が多いんです。
だからこそ病院によって新しい挑戦ができる。高齢化や医療従事者の減少で医療需要は増しているので、病院救命士の必要性もますます高まっていくかと。
実際、1年前よりも必要性が増していると感じる機会も増えています。そんな中で、私は幸運にも、病院救命士のパイオニア的な世代。今後、病院内での救命士の活躍の場を広げ、医療の現場の発展に、もっともっと貢献していきたいと思っています。
救命士の道を選ぶということは、「誰かの最も苦しい瞬間に寄り添う」ということです。現場は厳しいですが、その分「助かった」と家族が涙を流してくれる瞬間に立ち会える、本当に特別な仕事でもあります。
救命士の就職先は、消防勤務だけではない。これからは、病院救命士という選択肢もメジャーになり、ますます活躍の場が広がりそうだ。
お話を伺ったのは……
こちらの記事も要チェック!◆美容芸人・レインボー池田が「アロマテラピー検定」に挑戦!
◆心理系資格「難易度×活用方向」MAP
◆16タイプ別ベストな勉強法&人生右肩上がりの秘訣。
◆知的好奇心をくすぐられる「本の森ちゅうおう」に行ってみた
◆「まだ新しい自分になれる」福田萌が語る新たなキャリアへの一歩
文=堀池 沙知子